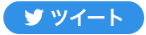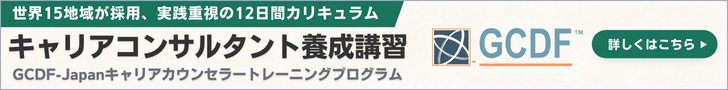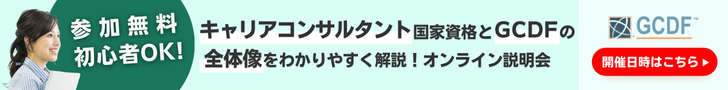キャリアコンサルタント養成講習 GCDF-Japan
オンライン説明会の予約受付中!
今すぐ日程を見る
正解のない人生。
歳を重ねていけば、いつか生き方や働き方の転換タイミングがおとずれると頭でわかっていても、いざ行動に結びつけるのはむずかしいものです。
近年は平均寿命が伸びたり、働く期間が長くなったりしている影響で、「50代になったら役職定年」「60代になったら引退」というような、年齢をきっかけにした働く節目は減りつつあります。一方で、年齢をきっかけとした制度を運営してきた社会が変化を受け入れるには時間が必要でもあり、シニアの活躍に向けて、社会は過渡期真っ只中のように思います。
今回は、ミドルシニアの特性、これからの働き方や生き方を考えるためのヒントをお伝えします。
この記事を読み、ワクワク、イキイキした日常への小さな一歩を踏み出していただけたら、とてもうれしく思います。
ミドルシニアとは?
労働市場における「ミドル層」「シニア層」について、明確に年齢区分を定義している文献は見当たりません。
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」では、高齢者を65歳以上とし、65歳から74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、生産年齢を15歳から64歳、年少を0歳から14歳としています。ここでは高齢者雇用安定法の55歳以上を高年齢労働者としています。
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
また、東京都指定管理事業である東京しごとセンターでは、以下のような年齢分けをしています。
ミドルコーナー・・・30歳以上54歳以下
※30歳以上34歳以下の方については、原則としてミドルコーナーのサービス(民間就職支援会社のアドバイザーによる再就職支援サービス等)のご利用となります(以下略)シニアコーナー・・・55歳以上
求人サイトや転職エージェントでは、54歳までをミドル、55歳以上をシニアとしているのも多くみかけます。サービスによっては、40代から60代を合わせて「ミドルシニア」としている場合もあるようです。
当記事では、おおよそ30代から54歳以下をミドル層、55歳以上をシニア層と定義します。
ミドルシニア、労働市場の現状
ミドルシニアの中でも50代から60代のシニア層については、人生経験が豊富で、職場での貢献度も高いにもかかわらず、働き方の選択肢は狭まりがちです。
しかし、人口減少に伴う労働力不足の中で、その価値が再評価されています。
企業はシニア層ならではのスキルや知識を活用したいと考えており、新しい役割が期待されています。
また、シニア層の人たちの中でも、これまでの経験を活かし、新たなチャレンジを求めてセカンドキャリアを模索する動きが活発化しています。
日本社会におけるミドルシニアの役割は、これからますます重要性を増していくでしょう。
今後は、彼らの持つ経験や知識を次世代にどうつなげるのかが問われているでしょう。ミドルシニア層は、ただ組織から課された労働を提供することだけでなく、職場でリーダーシップを発揮し、若手社員の育成や組織の風土改善に寄与することが期待されています。
また、これまでの人脈を活かして、新たなビジネスチャンスを生む可能性も大いに秘めているでしょう。
人口減少にともなうミドルシニア活躍への期待
日本は急速な人口減少に直面し、労働力不足が深刻な問題になっています。
企業は若年層だけでなく、ミドルシニア層の活用にも力を入れ始めています。最近では年齢に関係なく、経験豊富なミドルシニアを雇用する企業も少しずつ増えてきており、長年の経験に裏付けされた専門知識やリーダーシップが再び注目されています。
ミドルシニア世代の仕事の探し方と準備
ミドルシニア世代の仕事の探し方の特徴と準備の仕方について説明します。
年齢にとらわれず活躍できる仕事の見つけ方
年齢を重ねても、能力を最大限に発揮できる職場を選ぶためには、年齢に縛られない企業を探すことが重要になってきます。
近年では少しずつ、年齢にとらわれず雇用する企業も増えつつあります。
一般社団法人人材サービス産業協議会の調べによれば、ミドルエイジの人材を採用した実績のある企業の60%以上が、今後もミドルエイジの人材を採用したいと回答しています。
多様な働き方を受け入れてくれたり、年齢に関係なく実力を評価してくれる会社を、ネットや求人イベントなどを通じて調べることも有効でしょう。
出典:一般社団法人人材サービス産業協議会「中高年ホワイトカラーの中途採用実態調査」
さらに、業界イベントやセミナーに参加し、仲間とのつながりを作ることも大切です。これにより、自己成長の機会を広げると同時に、将来的なキャリアチャンスの可能性を高めることができます。
映画「マイ・インターン」の主人公に学ぶ
2015年に日本で公開された映画『マイ・インターン』。
すでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、この映画にはシニアがイキイキと生きるためのヒントがつまっています。
ロバート・デ・ニーロ演じる70歳の主人公は、引退生活に退屈を感じ、シニアインターンとしてネット通販会社で働きはじめます。当初はアン・ハサウェイ演じる40歳年下の女社長と合わずうまくいかなかったものの、徐々に信頼を得て活躍していくというストーリーです。
こういう活躍の仕方もあるのかという参考に、ご覧いただくのもおすすめです。
キャリアコンサルタント養成講習で自分を見つめ直す
キャリアコンサルタント養成講習では、専門家としての知識やスキルを身につけると同時に、自分自身のこれまでやこれからなど、自分についての理解を深めます。
なぜ、キャリアコンサルタント養成講習の中で自分について知る必要があるかといえば、いざ相談者を目の前にしたとき、自分について理解していなければ、無意識のうちに己の経験や価値観を前提に支援を進めてしまう危険があるからです。相談内容が個別化・多様化している昨今では、自分について理解しておくことはより重要性が高まっていると思います。
養成講習の中で、これまでの人生について他の人に話すことで、自分だけで考えていたときは気付けなかった人生への意味づけが見いだせることがあります。そして、次の一歩を踏み出すための勇気につながっていくのです。
高齢になっても維持できる知能がある
知能には「流動性知能」と「結晶性知能」の2種類があり、「結晶性知能」は高齢になっても上昇し続けるということが最近わかってきました。
独立行政法人労働政策研究・研修機構のコラムには、以下のように書かれています。
語彙や常識などの知識は成人期を通じて増え続ける。このような経験と知識の豊かさや正確さと結びついた能力を結晶性知能と呼び、学校教育や社会経験によって学習すると考えられている。業務処理の知識や仕事のスキルは、まさに結晶性知能そのものである。これに対して、図形処理のように情報を獲得し、処理する能力は 30歳くらいで頂点に近づき、40歳頃から低下するという。こうした能力を流動性知能というが、どちらかというと生得的な能力である。われわれが自覚する能力の低下は、たぶん流動性知能なのだろう。
結晶性知能は成人後も上昇し続けて 60代くらいで頂点を迎え、それから徐々に低下する。高齢者が再就職しようとする時、新たな仕事を学習することは困難なので、経験を活かすべきだと言われるが、これは理に適ったことだと考えられた。しかし近年の認知心理学研究によって、結晶性知能がどのように使われるのかを考えると、そうとばかりは言えなくなってきた。
年齢を重ねても新しい学習は習得できるという発見は、これからの人生を考える上でも勇気づけられるものでしょう。
2024年1月にキャリアカウンセリング協会で開催されたセミナー「シニアの幸福な働き方を考える―定年前と定年後のサードエイジを支援するヒント―」の中でも、法政大学の石山恒貴先生が結晶性知能について触れられています。興味のある方はぜひご視聴ください。
「シニアの幸福な働き方を考える―定年前と定年後のサードエイジを支援するヒント―」(2024年1月)
ミドルシニア世代を見据えてできる準備
キャリアコンサルティングやキャリア研修を受ける
いきなり将来を見据えて準備しましょうと言われてもむずかしいこともあると思います。キャリアコンサルティングやキャリア研修で専門家のサポートを受けながら、自身の強みや価値観をじっくり言語化していくのもよいです。
キャリア自律とは?定義や必要性、参考になる考え方や取り組み例を解説
趣味や好きなことをはっきりする
まずは、自分は何をしているときが楽しいのか、イキイキしているのかを明確にすることが充実した生活につながるでしょう。
もしわからないときは、興味のあることを体験してみたり、誰かに相談したりすることで「好き」「興味がある」などに気付けることもあるかもしれません。
2024年11月にキャリアカウンセリング協会で開催された講演で、野田稔先生は、ミドルシニアの人たちが元気に活動し続けるにはまず「自分はこうだ」というラベルを剥がすことが大事だと話されていました。ラベルを剥がす="変身"の疑似体験ができる場としては本格的な趣味や学びなどが挙げられています。
講演では、趣味が高じて活動が広がった方の紹介などもあり、今後を考える上での参考になるかもしれません。
野田稔先生「キャリアコンサルタントとしてミドルシニアの活躍支援に向き合う」(2024年11月)
活動範囲を広げ、普段しないことに参加してみる
あえて普段しないことをしてみたり、会わない人に会ったりすることでやりたいことを見つけられるかもしれません。
地域のイベント参加でも、趣味のワークショップでも、どこに気づきがあるかは未知です。興味を持ったものに勇気を出して挑戦することで、生涯を通じて取り組みたいと思えるものに出会える可能性もあります。
自ら仕事を創っていく経験を重ねる
会社や家族など、誰かの求めに応えることが得意な方は、一度「誰か」から離れて、「自分」の求めに応じて仕事ややりたいことを作る経験も大事になるでしょう。
健康管理と生活習慣のチェック
ミドルシニア世代になると、同級生の中にも持病を抱えたり、健康不安について話す機会も自然と増えてくると思います。
健康でいることは、元気に生きるための基本です。
日頃から食事のバランスや運動などを考慮しつつ、定期的に健康診断を受けて体力や精神力を維持しつづけましょう。
まとめ
最後に、ミドルシニアについてまとめました。
- ミドルシニア世代とは、おおよそ30代または40代から60代までをいい、明確な定義は存在しない
- 特にシニア世代の価値が再評価されつつあり、今後の労働市場では新しい役割が期待されつつある
- 近年は年齢にとらわれず雇用する企業も増えつつある傾向
- ミドルシニア世代を見据えた準備も大事