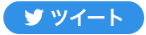キャリアコンサルタント養成講習 GCDF-Japan
オンライン説明会の予約受付中!
今すぐ日程を見る

「悩んでいる人の役に立ちたい」「人の気持ちに興味があり、心理学を学んで社会貢献したい」「心の健康についての問題解決を支援したい」・・・カウンセラーという職業や人に興味を持つ方も多いのではないでしょうか。
近年、心理的な支援へのニーズは高まってきており、カウンセラーの活躍の場も広がりつつあります。
今回は、カウンセラーを目指すために必要な主な資格と仕事の内容、カウンセラーになるまでのプロセスについてご説明します。
この記事を読むと、カウンセラーになるためにまずは何を検討すべきか、わかるようになっていることでしょう。
カウンセラーとは?
カウンセラーとは「カウンセリングを行う者」の呼称です。
カウンセリングを行う者が「カウンセラー」と呼ばれるのに対して、カウンセリングを受ける者は「相談者」「クライエント」「クライアント」などと呼ばれます。
では「カウンセリング」とはどのような行いなのか、詳しく説明します。
カウンセリングとは「心理的な専門的援助過程」を指す
「カウンセリング」に対してどのようなイメージを持っていますか?
「普段は話しづらい悩みを聞いてもらえる」「話を聞いてもらってスッキリできそう」「自分の気づいていなかったクセにきづけそう」など、さまざまあるかと思います。
キャリアコンサルタント養成講習「GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム」のテキストでは、カウンセリングの定義について以下のように述べられています。
ハー(Herr, E. L.)とクレイマー (Cramer.S.H.)によって、多くの定義に共通する要素が定められています。
「カウンセリングとは、心理学的な専門的援助過程である。
そして、それは、大部分が言語を通して行われる過程であり、その過程のなかで、カウンセリングの専門家であるカウンセラーと、何らかの問題を解決すべく援助を求めているクライエントとがダイナミックに相互作用し、カウンセラーはさまざまの援助行動を通して、自分の行動に責任をもつクライエントが自己理解を深め、「よい(積極的・建設的)』意思決定という形で行動がとれるようになるのを援助する。そしてこの援助過程を通して、クライエントが自分の成りうる人間に向かって成長し、成りうる人になること、つまり、社会のなかでその人なりに最高に機能できる自発的で独立した人として自分の人生を歩むようになることを究極的目標とする」。
カウンセリングは、相談者が自分で意思決定し、行動できるようになることを目標にしています。
意思決定するのも行動するのもカウンセラーではなく、相談者自身であり、カウンセラーはサポートに徹します。
現在、カウンセリングの定義や技法はさまざまあります。カウンセラーを目指すにあたっては、まずは、さまざまなアプローチや理論に共通した基礎を理解することが大切です。
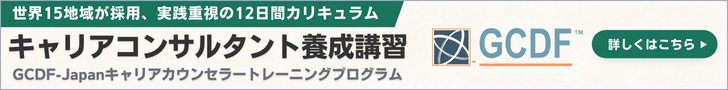
カウンセリングと心理療法には異なる点も
厚生労働省の「e-ヘルスネット」によれば、カウンセリングと心理療法は厳密には異なる点があると述べられています。
カウンセリングは、主に心理の専門家がクライエントや患者の話を傾聴したり受容したりしながら、クライエントや患者の心情や状況の理解に努めることによって、主体的に問題の解決を行っていけるようにサポートすることを指します。
一方で、心理療法はより医学的モデルによる要素が強く、標的となる症状や状態あるいは解決したい問題などに対しての改善や解決を目的として行われることが一般的です。心理療法には来談者中心療法、認知行動療法、精神分析的心理療法、遊戯療法、家族療法、問題解決療法などいくつかの技法があるほか、近年は患者の状態・状況に合わせて最適なアプローチを選択する「統合折衷型アプローチ」と呼ばれる技法も増えてきています。また、近年は科学的立場に基づく「本当に効果のある方法」による介入が重視されてきており、実証的な証拠(エビデンス)に基づく支援の必要性が強調されるようにもなっています。
カウンセラーの活躍の場
カウンセラーの主な活動の場をご紹介します。
病院・クリニックなどの医療機関
- 医療機関
幅広い年齢層の人のカウンセリングを行い、相談内容は生活や家庭・職場などかなり多岐にわたります。
精神科医からの指示で、専門的な技法を用いてカウンセリングを行います。対話を通じて相談者との信頼関係を構築し、相談者本人が問題を整理したり問題解決に向かっていくとともに、精神症状を緩和できるような心理的支援を行います。
精神科や心療内科以外の診療科では、緩和ケアや慢性疾患などの患者や家族の心理相談に応じることもあります。出典:job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))「カウンセラー(医療福祉分野)」
保健施設・福祉施設など
- 保健所
地域住民の健康を支える広域的・専門的・技術的拠点と位置づけられる施設で、難病や精神保健に関する相談などの専門性の高い業務を行っています。保健所では、精神疾患、ひきこもりやアルコール依存症などの心の健康相談を受け付けており、相談内容によっては、関係機関や医療機関へ紹介することもあります。
出典:厚生労働省「保健所の活用の仕方~どんな時に頼れば良いの?~」 - 精神保健福祉センター
各都道府県に設置されている精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関です。
特に精神保健や精神障害者福祉に関する相談や指導は、複雑または困難なものを行っています。具体的には、心の健康相談から、精神医療に係わる相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、薬物、引きこもり、思春期、認知症状などの特定相談を含めた精神保健福祉全般の相談です。
センターによって異なるものの、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士などの専門職がいます。
出典:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「こころの情報サイト 公的機関の相談」・厚生労働省「職場における自殺の予防と対応」
- 児童相談所などの児童福祉施設
子どもが心身ともにすこやかに育つよう、子どもと家庭などを援助するために相談援助活動をする施設です。原則18歳未満の子どもに関する相談を、本人や家族などから受け付け、問題解決に向けて支援します。
小・中・高・大学など
- 学生相談室
校内で、登校困難や集団行動がむずかしい生徒やその保護者、教職員からの相談に応じる「スクールカウンセラー」と呼ばれる職業があります。
文部科学省の調査によれば、スクールカウンセラーは非常勤職員で、その8割以上が臨床心理士です。不登校やいじめ、友人関係、親子関係などの多岐にわたる相談に応じています。
出典:文部科学省「スクールカウンセラーについて」
- キャリアセンター
卒業後の就職や進路の悩みについて、キャリアコンサルタントやキャリアカウンセラーが相談に応じます。
企業
- 相談室
従業員からの健康相談やメンタルヘルスに関する相談に応じます。
企業によってはハラスメントの窓口を兼ねている場合もあります。産業医や臨床心理士、産業カウンセラーなどが対応します。近年では「EAP」と呼ばれる従業員支援プログラムを外部委託している例もあります。
出典:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳 社内相談窓口を設置している企業の取組事例」・厚生労働省 e-ヘルスネット「EAP / 社員支援プログラム」 - キャリア相談室
キャリア支援室などで、キャリアコンサルタントが相談に応じます。
法務省関連機関など
- 少年鑑別所・少年院・刑務所・保護観察所など
心理学の知識を活かして、対象者の立ち直りに向けた処遇指針の提示や刑務所の改善指導プログラムの実施に携わります。
出典:job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))「法務技官(心理)(矯正心理専門職)」
その他
NPOや一般社団法人などで、生きづらさや孤独などに悩む方の相談に応じます。電話相談に加え、最近はSNSやチャットで相談できる機会も増えています。
出典:一般社団法人 日本臨床心理士会「臨床心理士の活動の場」
カウンセラーになるには?

カウンセラーになるために、まず知っておきたい3つのポイントをご説明します。
活動分野や方向性を検討する
カウンセラーの活動分野や方向性、相談内容は非常に多岐にわたります。活動したい分野によっては、学び方も就業に必要となる資格も異なってきます。
どのような場で、どのような分野でこころの支援をしていきたいのか、まずは自身が目指したい方向性を決めておくことが必要です。
心理学に関連した資格取得が有効
「カウンセラー」とは職種の名称であって、カウンセラーと名乗るために何か資格が必要ということではありません。ただし、カウンセラーの求人では、何らか心理学に関連した資格の保持を求められることが一般的です。
例えば、医療機関でカウンセリングに従事するなら臨床心理士や公認心理師、企業内でのメンタルヘルスの維持向上なら産業カウンセラー、キャリア支援をするならキャリアコンサルタントなどです。
資格を取得するために学校やスクールで学ぶ
資格を取得するためには、まずはカウンセリングを実施するために必要な知識や技能を学び、習得する必要があります。学習内容は、取得したい資格の受験条件によっても異なります。
例えば、公認心理師であれば心理学系の大学卒業と大学院修了、臨床心理士であれば大学院修了が受験に必要となります。民間のカウンセラー資格であれば、スクールに通うことが一般的です。
代表的な資格
日本において代表的な、心理学に関連した資格を紹介します。
公認心理師
公認心理師は、心理職では日本で唯一の国家資格とその有資格者のことです。
厚生労働省のサイトでは、公認心理師について以下のように述べられています。
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
臨床心理士
臨床心理士は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する公的資格とその有資格者を指します。
認定団体のサイトによれば、「臨床心理士」とは、臨床心理学にもとづく知識や技術を用いて、人間の“こころ”の問題にアプローチする“心の専門家”です。
臨床心理士には4種の専門業務があります。
- 臨床心理査定
さまざまな心理テストや観察面接を通じて、個々人の独自性、個別性の固有な特徴や問題点の所在を明らかにします。同時に、心の問題で悩む人をどのような方法で援助するのが望ましいのか、明らかにしようとします。- 臨床心理面接
相談者の心の支援に資するもっとも中心的な専門行為です。来談者の特徴に応じて、さまざまな臨床心理学的技法を用いて支援します。- 臨床心理的地域援助
地域住民や学校、職場に所属する人々(コミュニティ)の心の健康や地域住民の被害の支援活動を行います。- 上記1-3に関する調査・研究
心の問題への援助を行っていくうえで、技術的な手法や知識を確実なものにするために、基礎となる臨床心理的調査や研究活動を実施します。
公認心理師と臨床心理士を比較
公認心理師と臨床心理士について、一覧で比較しました。
| 公認心理師 | 臨床心理士 | |
|---|---|---|
| 資格の種類 | 国家資格 (公認心理師法) |
公的資格 (公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定) |
| 始まった年月 | 2017年 | 1988年 |
| 主な養成課程 | 大学で心理学系の科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業後、大学院において心理学系の科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修了し修士号取得、または認定施設における2年以上の実務経験 | 臨床心理士養成に関する指定大学院または専門職大学院の修了 または医師免許取得者で心理臨床経験2年以上 |
| 養成にかかる最短所要期間 | 6年間 | 2年間 |
| 資格者数 | 69,875人*1 (2023年3月末現在) |
40,749人*2 (2023年4月現在) |
| 試験実施機関 | 一般社団法人 日本心理研修センター(文部科学大臣および厚生労働大臣指定) | 公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 |
| 試験の実施頻度 | 年1回 |
年1回 |
| 試験の形式 | 五肢・四肢択一式試験 | 多肢選択方式試験 論文記述試験 後述面接試験 |
| 合格率 | 73.8%*3 (2023年5月実施、第6回試験) |
64.8%*4 (2022年) |
| 資格更新の有無 | なし | あり(5年ごと) |
出典:
厚生労働省「公認心理師」「公認心理師法」
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会「資格審査の実施」
*1 *3 一般財団法人 日本心理研修センター「第6回公認心理師試験(令和5年5月 14 日実施)合格発表について」
*2 *4 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会「『臨床心理士』資格取得者の推移」
産業カウンセラー
産業カウンセラーは、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格とその有資格者のことです。
認定開始が1992年と国内の心理学関連資格の中では歴史のあることや、2001年まで公的資格であったことから、知名度の高い資格のうちのひとつです。
産業カウンセラー協会のサイトによれば、下記の3つを活動領域としています。
- メンタルヘルス対策への支援
職場におけるメンタル不調の予防から危機介入、職場復帰への支援、ストレスチェック後のフォローなど幅広い領域に対応します。- キャリア形成への支援
働く人々のキャリア教育およびキャリアカウンセリングなどを行います。- 職場における人間関係開発・職場環境改善への支援
人と組織と協働し、グループファシリテーション能力の開発などの研修や、組織診断による職場環境改善の提案などを行います。
産業カウンセラーは、「産業カウンセラー養成講座」を6ヶ月間受講することで受験資格を得られるため、大学卒業や大学院修了などを条件とする心理学関連資格よりも、比較的資格取得しやすいことも特長です。2022年度の合格率は、58.4%となっています。
出典:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会「協会について」「合否結果について」
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントは、2016年からはじまった国家資格です。
労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導などのキャリアコンサルティングを行う専門家で、カウンセリング技法やキャリア発達理論などの心理学の知識をベースにキャリア相談*に応じます。
次の章でさらにくわしくご説明します。
*キャリア相談に訪れた相談者が、こころの病気にかかっている可能性がある場合、キャリアコンサルタントは病院などの専門機関を紹介することがあります。例えば、うつ病の可能性のある相談者に対して自分を深く見つめるカウンセリングを行うことは、病気を悪化させる可能性もあり、禁忌とされています。
出典:『GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム テキストブックEx』株式会社リクルートマネジメントソリューションズ、2020年、p.31より引用
キャリアカウンセラーからキャリアコンサルタントへ

キャリアカウンセラーは、カウンセラーという職業の中でも「相談者のキャリアの問題に焦点をあてて専門的に援助する職務」と言えます。
日本にはさまざまな「キャリアカウンセラー」の資格が存在します。
2016年に国家資格キャリアコンサルタントが法制化されたことにより、キャリア支援資格の主流は民間のキャリアカウンセラー資格から国家資格キャリアコンサルタントに移りました。
国家資格の名称が「キャリアカウンセラー」ではなく「キャリアコンサルタント」である背景には、「カウンセリング」という用語が、一般的に臨床場面での心理療法を想起させるという強い懸念があったとされています。以来、労働行政では「キャリアコンサルタント」「キャリアコンサルティング」という和製英語が使われています。
【関連記事】
キャリアカウンセラーとは?キャリアコンサルタントとの違いも解説
キャリアコンサルタントとは?資格取得までのステップと試験合格後の手続きを解説
キャリアコンサルティングは働く人に対するキャリアカウンセリングそのもの
キャリアコンサルタントが行う「キャリアコンサルティング」とは、まさに働く人に対する「キャリアカウンセリング」そのものとされます。
キャリアカウンセリングとは「人が職業生活を送っていく上で関連するあらゆる問題を対象とするカウンセリング」です。キャリアカウンセリングで扱う問題は、「働くこと」にまつわる自由時間、余暇、学習、家族との活動などを含んだ個人の生涯にわたる生き方(ライフスタイル)の過程すべてが含まれます。
出典:『GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム テキストブック1』株式会社リクルートマネジメントソリューションズ、2020年、p.27より引用
キャリアカウンセリングは、アメリカで発達し、日本に輸入された概念・活動です。1980年代後半に国内企業の間で急速に広まったのち、高校や大学などの教育機関や行政機関にも広まり、現在に至ります。
【関連記事】
キャリアカウンセリングとは?注目される背景や期待される効果も解説
キャリアカウンセリングと他のカウンセリングとの違い
キャリアコンサルタントは、公認心理師や臨床心理士のように臨床現場で心理療法を行うようないわゆる「心理職」ではありません。ただし、カウンセリングの技法やキャリア発達理論などの知識が必要です。
『6訂版 キャリアコンサルティングの理論と実際』では、著者の木村周氏がキャリアカウンセリングと他のカウンセリングとの違いを要約しています。
- カウンセリングの目的が、問題行動の除去や治療ではなく、個人のより良い適応と成長、個人の発達を援助することに重点を置く
- 進路の選択、職業選択、キャリア・ルート決定など具体的目標達成を目指して、カウンセリングを行う
- カウンセリングは特定理論や手法にとらわれず、さまざまな理論や手法を使用する
- カウンセリングが、自己理解、職業理解、啓発的経験、方策の決定と実行、フォローアップのガイダンスと一体となって行われる
- 「システマティック・アプローチ」と呼ばれるカウンセリング・モデルを使い、カウンセリング・アプローチは折衷的である
- カウンセリングのみでなく、コンサルテーションや関係者の協力、教育の機能を重視する
- キャリアカウンセリングの実践にあたっては、学校教育、職業紹介機関、および職業能力開発機関において、それぞれの法律に基づいておこなわれる。
キャリアコンサルタントの仕事内容と活動の場
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、キャリアコンサルタントは、相談やカウンセリングといった一対一の相談活動に従事している割合が高いです。ハローワークなど需給調整機関のキャリアコンサルタントでは一対一の相談が多く、学校や教育機関に所属するキャリアコンサルタントは、セミナーや研修などの講師が多い傾向があります。
キャリアコンサルタントが行っている活動では「相談、面談、カウンセリング」が約6割で最も多く、「セミナ―、研修、授業の講師」などが続きます。
【関連記事】
キャリアコンサルタントとは?資格取得までのステップと試験合格後の手続きを解説
資格取得するには
キャリアコンサルタントの資格を取得するには、約2ヶ月から5ヶ月間のキャリアコンサルタント養成講習を受講し、キャリアコンサルタント国家試験の受験条件を満たすことが一般的です。
カウンセラー資格についてのまとめ
カウンセラーの資格についてまとめました。
- カウンセラーとは「カウンセリングを行う者」のことを指す
- カウンセリングの究極的目標は、相談者が自発的で独立した人として自分の人生を歩むようになること
- カウンセラーの活躍の場はさまざま、活動分野や方向性に合わせた資格取得が有効
- カウンセラーの資格は、公認心理師・臨床心理士・産業カウンセラーなどがある
- キャリアカウンセリングをベースとした国家資格に「キャリアコンサルタント」がある
- 学校やスクールに通学、受講の上で受験資格を得ることが一般的